
- Class
- 授業紹介
- Class
- 授業紹介
- Class
- 授業紹介
公共経営学科の授業紹介
社会経営系
地域経営系
地域経営論

担当:本多 哲夫
地域を元気にすること、つまり、地域を振興することはとても重要なことですよね。私たちが住んでいる地域が停滞していると、私たちの生活が貧しくなったり、安心・安全に暮らせないということになりかねません。地域経営論では、どのように地域を振興していけばよいのかを考えます。地域を振興していくには、国に頼るだけではなく、地域の中のいろいろな人たちが連携して、地域に合った独自の振興の仕方を見つけ出していく必要があります。授業では、とくに、地域に根付いている中小企業と地元の政府である自治体に注目しながら、地域振興のあり方について皆さんと一緒に考えていきます。
地域経済論

担当:松永 桂子
現代の都市・地域が直面しているのは急速な人口減少と高齢化など、今までに経験したことのない大きな環境の変化です。広がる格差を是正し、自然環境やまちの景観を保全しながら、新たな産業や豊かな生活文化を育んでいくにはどうすればよいのでしょうか。わたしたちは、経済成長の時代とは違う転換期に立っています。
維持可能な社会や経済のあり方について、地域を対象に考えていくのが地域経済論の基本的な考え方です。たとえば、社会の課題を新たな産業やビジネスに結びつけ、地域のなかで機能する仕組みを考え、実践していくことも盛んになりつつあります。それはソーシャルビジネスといい、新たな経済の担い手として期待されていますし、若い世代の関心も高まっています。地域での具体的な取り組み、ビジネスを通して、維持可能な社会や経済のあり方について考えてみましょう。
地域デザイン論

担当:松永 桂子
商学部で学ぶ「デザイン」とは、どのような授業をイメージしますか?デザインと聞けば、建築やファッション、グラフィックなどが思い浮かぶでしょうか。しかし、最近では、社会デザイン、コミュニティデザインといった言葉も浸透しはじめ、主体的、能動的に社会や地域を変えていく概念として広く使われています。
たとえば、商店街の空き店舗を活用して、スモールビジネスを展開し、にぎわいを創出したり、人口減少地域に移住者を呼び込み、新しい仕事をつくっていったりするのも、そのひとつです。いろいろな取り組みがあげられますが、仕組みを考え、実行し、さらには利益(公益)を生んでいくという点では、ビジネスに似ている面もあります。実際の取り組みを見聞して、ビジネスと地域社会の関係、地域デザインの実践方法について、学んでいきましょう。
中小企業論

担当:本多 哲夫
企業のことを学ぶと聞いたときに、トヨタやパナソニックのような大企業をイメージする人も多いのではないでしょうか。しかし、実は、企業数全体の9割以上は中小企業であり、労働者の約7割は中小企業で働いています。そして、中小企業は大企業とは異なる特性や問題を抱えています。したがって、企業のことを学ぶという際には、中小企業について学ぶことも重要なのです。しかも、中小企業のことを学ぶことで、社会、経済、地域のことをより深く広く知ることができます。中小企業論では写真や動画などで身近な中小企業事例を紹介しながら、臨場感たっぷりに楽しく中小企業のことを学んでいきますので、ぜひ受講してみてください。
中小企業経営論

担当:本多 哲夫
中小企業経営論では、中小企業の経営者を毎回お招きして、実際の経営の苦労や喜び、課題などについてお話しいただきます。また、学生から経営者に対して、自由に質問し、答えてもらいます。実際の経営者のお話を直接聞く機会、質問する機会はなかなかありませんので、貴重な講義です。経営者が自らの体験から語るお話というのは、生々しく、ドラマティックで、胸に突き刺さる感動的なお話が多いです。笑いあり涙ありです。企業経営や中小企業の実態についてとてもよく理解できますし、皆さんの今後の就職活動やキャリア形成の際にも参考になると思います。
大阪ビジネス論

担当:富澤 修身
戦前の大阪には、大大阪(だいおおさか)と言われた時期がありました。東京を抜いて日本一の大都市となった時期です。当時の大阪は、大工業都市であったと同時に、商人が大活躍する都市でもありました。現在の大阪は、日本一の大都市ではありません。それは新しい産業が東京圏や名古屋圏で成長してきたことと関わっています。しかし、ここ数年は、海外からの旅行者による消費(インバウンド消費)によって、大阪への関心が再び高まっています。大阪が得意とする医薬品産業や医療機器産業への注目も集まっています。新製品の試作では、大阪の中小企業の多様なもの作り能力が高く評価されています。講義では、大阪ビジネスの歴史と特徴を明らかにし、そのメリットを活かした飛躍のあり方について論じる予定です。
地域産業・まちづくり系
地域産業論

担当:本多 哲夫
地域産業論は、地域産業振興に関わっておられる自治体の職員の方々をお招きして、政策の実態や課題についてお話をしていただくという授業です。地域の産業を振興していくというのは大事なお仕事なのですが、案外、その実態は知られていないことが多いです。ですので、地域産業振興がどういう形で行われているのか、どんな経緯で行われてきたのか、どのような意図で実施しているのか、などなど、実際に政策にたずさわっている自治体職員の方々からお話しをうかがうというのは、とても貴重です。地方公務員がどういうお仕事をしているのか興味がある人にもお薦めの授業です。
地域金融論

担当:清田 匡
ずっと同じ地方で生活していると気づきにくいかもしれませんが、地域によっていろんなものがずいぶん違っています。街並みや方言がちがうだけなく、経済も異なっています。その地方で活動している企業や産業が異なるからです。産業が異なると、必要な資金の性質や大きさ、必要なタイミングも異なり、金融機関へのニーズも異なってきます。そしてそれ自身の収益をあげるためには、地域経済の活性化をめざさなければならいという公共的な性格を地域金融機関は持っています。地域金融論では、各地域の経済や産業の特徴と、金融機関の活動のこのような関わりについて講義します。
ベンチャー・ビジネス論

担当:新藤 晴臣
「ベンチャー・ビジネス」というと、ソフトバンクや楽天、アップルといった、創業者がゼロから立上げ、成長させたビジネスが頭に浮かぶと思います。そうしたビジネスは、なぜ成長したのでしょうか?創業者が優秀だったから、たまたま運が良かったから、良い仲間や社員に恵まれたからなど、さまざまな原因が考えられます。この授業では、実際の創業者やベンチャー・ビジネスの事例を通じて、成功と失敗の原因を議論していきます。また授業の後半では、皆さんが架空のベンチャー・ビジネスの「創業者」となり、そのビジネスプラン(事業計画)をつくってもらいます。皆さんと一緒に、ビジネスの冒険(ベンチャー)に出られることを楽しみにしています。
ベンチャー・マーケティング論
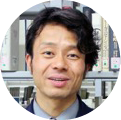
担当:小沢 貴史
私達は、色んな製品やサービスに囲まれて生活しています。そんな中、『そぅそぅ、こんな製品が欲しかったんや!』と思う瞬間って、ありませんか?
この講義では、私達の身の回りで、まだ満たされていないニーズを見つけ出して、それを満たすための戦略を探究します。「売れる理由」を創り出すために、私達のできることは何かを、考え抜きます。
何か相手に役立ててもらえるモノや、為になるコトはないんやろか…そのカギを、「マーケティング論」で探してみて下さい。都市で活動する大手企業だけでなく、地域を拠点に活躍する中小企業や非営利団体に行政組織など、どの活躍の舞台でも役立つ智を、一緒に探究してみませんか。
舞台を問わず、何かをトコトン追い求め、伴われるリスクや失敗を恐れずに、様々な障害を克服して、志を実現しようとする人達の背中を後押しする…ここに、「ベンチャー」たるゆゑんがあります。
地域マーケティング論

担当:小林 哲
「地域はわかるけどマーケティングって何?」マーケティングとは、相手のしたいことに応えることで、自分のしたいことを実現すること。たとえば、ある地域が自分のことをもっと知ってほしいと思うならば、相手が何に興味を示すかを考え、その興味に応えることで相手の自分に対する注目度を高める。これが、地域マーケティング(地域をマーケティングすること)です。もともとマーケティングは、ビジネスの中で培われてきた知恵。その知恵を地域のために活用することで、その地域にかかわる様々な人々を満足させながら、自らも目的を達成し満足する。そんな地域のWIN-WIN関係を築くための方法を学ぶのが地域マーケティング論です。
都市型産業論

担当:富澤 修身
私たちの周りには、さまざまな産業があります。そのうち産業の誕生・成長・発展・成熟が都市と深く関わっている産業群を都市型産業と言います。都市の人口と需要、都市に集中する中小零細企業群、都市にある人材等の資源や歴史・文化に育まれて展開する産業群です。こうした産業群のうち、都市型産業論では身近なファッションを中心にすえて、講義を進めます。ファッションは、都市で生まれ都市で広まりますし、個々の都市の個性と文化を大きく反映するからです。また、パリの影響力に見られるように、都市の文化的パワーの強弱も反映するからです。講義では、模倣から創造へという視点に立って、大阪、東京、ニューヨーク、上海、ソウルのファッション産業について取り上げる予定です。
産業地理系
産業立地論

担当:鈴木 洋太郎
私たちが生活している地域社会は、自動車産業や家電産業、外食産業、コンビニ産業など様々な産業活動(ビジネス分野)によって成り立っています。産業立地論は、地理的・場所的な側面に注目しながら、ビジネスに関する諸問題について研究します。「自動車産業の世界的大企業であるトヨタは、なぜ愛知県豊田市に多数の工場を集中しているの?」、「コンビニ産業では、セブンイレブンやファミリーマートなど同じ企業の店舗がすごく近くに立地していますが、それって無駄じゃないの?」などなど。産業立地論を学ぶと、ビジネスや地域社会を発展させるためのヒントや課題が見えてきます。
産業集積論

担当:立見 淳哉
経済学の教科書では経済活動の地理的な広がりが出てくることは滅多にありません。しかし、何気なくみている日常の風景を少し注意してみると、お店や工場が集まっている場所があることに気がつきます。なぜお店や工場(しかも特定のジャンルに偏ったもの)が特定の場所に集まるのでしょうか。しばしばある業種にのみ有効な「場所の魅力」があるからです。では、「場所の魅力」とはなんなのでしょうか。いろいろなパターンがありそうです。講義ではこのちょっとした謎について、なぜ企業が集まるのか、どんな業種構成か、集まるとどんなメリットがあるのか、そのための条件と何か、といったことについて理解したいと思います。
都市・地域産業論

担当:立見 淳哉
今、都市に暑い視線が注がれています。都市は多種多様なタイプの人や産業が集まり、アイデアを交換し、これまでにない新しい製品やサービス、課題の解決方法を生み出す力を持っているからです。特に、ファッション、建築、デザイン、ソフトウェア開発、広告、新しいクラフト産業など、個人の創造性が鍵となる創造産業は、都市に集中する傾向があります。これらの産業では、今の時代に特徴的な、働き方、能力のあり方、人間関係、暮らし方、価値づけの仕方が、顕著に見られると言われています。講義では創造産業を中心に、産業活動の中身とあわせて今という時代の特徴について考えてみたいと思います。
産業立地論

担当:藤塚 吉浩
商店街にスーパーマーケットができると便利になったかもしれませんが、それが閉店すると商店街でも買い物に困ることはありませんか。また、操業していた工場が他の地域に移転してしまうと、大勢の人たちで賑わっていた工場の周辺から活気は失われました。とはいえ一部の地域では、昔の工場や商店の建物を活用して、新しい店舗になったところもあります。この講義では、地域の衰退の原因を探るとともに、どのようにすれば地域が再生されるのか、詳しく考えます。
都市・地域分析論

担当:藤塚 吉浩
都市のあるところで人口が増えて、他のところでは人口が減っています。それがいつ頃から起こっているのか、人口といってもどのような人たちが増えたり、減ったりしているのかについて、地図に描くととてもわかりやすくなります。地図に示すことで、新たな問題を見つけることもできます。この講義では、テーマに即した地図の描き方とともに、都市と地域の問題を分析する方法を学びます。








公共経営論
担当:廣瀬 喜貴
地方自治体や国は、住民のためにどのような経営を行なえばよいのでしょうか。また、非営利組織は受益者のためにどのような経営を行なえばよいのでしょうか。公共経営論では、これまでの経営学研究で積み重ねられてきた知識にもとづいて、この難問について考える授業を展開します。イメージとしては、公会計論で外部に向けた会計情報のディスクロージャーを主に取り扱うのに対して、この公共経営論では、内部の人たちがうまく経営するための方法を学びます。経営学の知識のみならず、財政情報や会計情報を内部管理に役立てるという視点も持ちつつ、皆で公共経営について考えましょう。
▲トップへ戻る